頭がいいを頭をつかって考える
目次
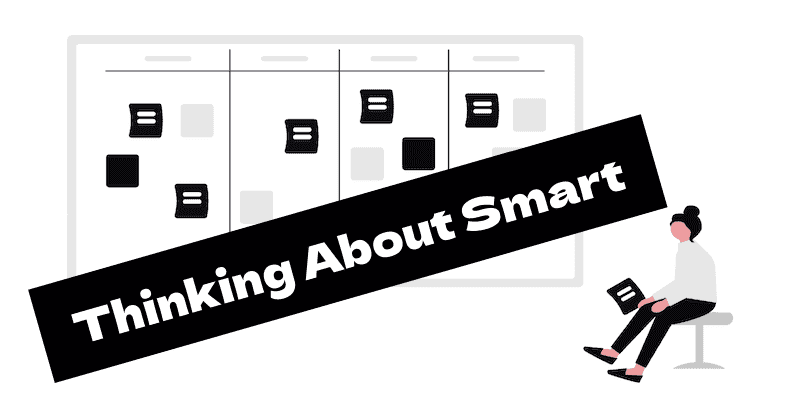
今日は 頭のわるいやつが考えた頭の良さについての記事 です。
内容は一応まじめ(のはず)ですが記事の品質は推して知るべしなので、ヒマな方はポエムだと思って気軽に読んでください。
この記事について
本稿は6年ほど前に当時いた会社のひとたちで行っていたアウトプット会という何でも勉強会的なイベント向けに書いた記事です。その名前のとおり、とくにテーマの縛りはなく、何かしらのアウトプット、言語化を行い、メンバーのみんなに発表するというものでした。
この会は月1回程度あり、その度に発表者が1人、残りのメンバーは発表に対して質問したり、意見や感想を言ったり、というのが大まかな流れで、基本的には終始和やかな雰囲気で楽しかったです。
当時の同僚にふと声をかけられ、勢いで参加してみたんですが、参加日にいきなり自分が発表担当となったのでその際に発表したのが今日の記事になります。
自分が退職してからも何回かはこのイベントに参加し続けていたんですが、いろいろあってメンバーが散り散りになりました。みんな今も元気かなと思いを馳せつつ、せっかくなので自分の発表記事を公開してみることにしました。
ということで次項からは当時書いた記事の転載になります。
大した内容ではないですが、興味のある方はお付き合いください。
はじめに
「頭がいい」という言葉は、日常でよく耳にします。しかし、いざ考えてみると、その意味は人によって異なります。理解が早い人、説明がうまい人、記憶力が抜群の人など、さまざまなケースがあります。
そこで本記事では、私なりに「頭がいいとは何か」「頭を良くするにはどうすればいいか」を整理してみました。これはあくまで私の持論であり、みなさんのご意見をいただくための叩き台です。
頭がいいとは
私が「頭がいい」と感じた場面を思い返すと、次のような特徴がありました。
- 人の話や出来事の理解が早い
- 数字の計算が速い
- 物事の説明がわかりやすい
- 思いがけないアイデアを出す
- 知識が豊富
- よく覚えている
これらを整理すると、大きく 「思考力」「発想力」「記憶力」 の3つに分類できると考えます。
つまり「頭がいい」とは、このいずれかに優れていることを指す場合が多いのです。
頭を良くするには
結論から言うと、頭を使うこと が頭を良くする一番の方法だと考えます。日頃の人間観察による主観ですが、頭のいい人ほど普段から頭をよく使っているように見受けられます。
そのため、「頭がいいから頭を使う」のではなく、むしろ「頭を使うから頭がよくなる」のではと考えました。
ここで大事なのは、頭のよさには先天的な差はあれども、訓練である程度伸ばせる ということです。人生まだ希望がありますね。
目的別「頭を使う」練習
ということでここからは具体的な訓練の方法論を考えていきたいと思います。目指す頭の良さによって、鍛え方は違いますがここでは3つに分けて考えてみます。
1. 思考力をつけたい
https://www.weblio.jp/content/%E6%80%9D%E8%80%83%E5%8A%9B
思考
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/04/07 23:06 UTC 版)思考(しこう、英: Thinking)は、考えや思いを巡らせる行動であり、結論を導き出すなど何かしら一定の状態に達しようとする過程において、筋道や方法など模索する精神の活動である。
思考力は名前のとおり「考える力」です。
一般的に頭がいい、で一番連想されるのがこのタイプだと思います。
深く物事を考えられるタイプで、このタイプは 地頭がいい などと言われることもある印象です。人の話を理解するのが早いのも相手の話を聞いて、解釈することに頭を使い続けられた結果ではないかと考えています。
練習のポイントは 考えを止めないこと と考えます。
例えばこんなトレーニングはいかがでしょうか。
- 家計簿をつけて数字の増減を意識する
- 買い物で税込み→税抜き価格を計算する
- 推理小説を読み、犯人を推理してみる
- パズルやクイズゲームを解く
- 他人のコードを読み、意図を推測する(同業者に限りますが)
ここにないものでもいい方法はたくさんあると思います。
「頭を動かし続けること」によって負荷をかけることがポイントで、これができるならなんでもよいと思います。筋トレと少し似た考え方です。
2. 発想力をつけたい
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BA%E6%83%B3
これはいわゆるアイデアマンを目指したい人が該当すると思います。ある日、ある時突然閃いた!なんて素敵ですよね。
発想力は「新しいアイデアを生む力」です。
鍵は リラックスすること です。有名なひらめきも、散歩中や入浴中などリラックス時に生まれたケースは枚挙に遑がないです。有名な ブレインストーミング などもリラックス状態を作ることに重きが置かれています。
なので私は発想力の鍵は リラックス状態を作り出す ことと考えます。
- クイズ番組を見て気軽に考える
- ゲームやなぞなぞで遊ぶ
- 自分なりの「リラックスルーティン」を持つ
そもそも「誰にでも発想力はある」からあとは自分の発想力を100%発揮できれば成果は出るはず、と前向きに取り組む姿勢が大事です。
3. 記憶力をつけたい
つけたいですね、記憶力。
これは一般的にはいろいろ言われてますが、もっともスタンダードかつ、正解と言える結論はこちらではないでしょうか。
覚える=思い出す
どういう話かというと、人間の記憶は思い出そうとすることで定着する というものですね。
覚えようとするのではなく、思い出そうとすることが大事です。アウトプット重視ということですね。
受験勉強方法の一貫に、いきなり過去問を問いてみる というものがあります。これは本来わからないことを洗い出すことが目的ですが、自分の記憶、知識から思い出そうとする という効果も含まれています。そのため、問題演習を先にやることですでに一度思い出そうとトライしているため、復習の効果が高くなる、というメリットもあると考えます。
また、別の例としては、忘れないようにするために備忘録等に残しておいたものは意外と忘れずに覚えていたりする、なんてことはないでしょうか? 忘れてしまうのは往往にして記録に残していない(つまり思い出そうとしていない)ものが多いです。 (個人の感想含む)
というわけで、物事を覚えたい方は、まずどうやってアウトプットをするかを決めておくのが定着への近道だと思います。
繰り返しますが 覚える=思い出す です。
さいごに
先天的な頭の良さの差は確かに存在します。
しかし「どうせ自分は頭が悪い」と諦めるより、頭は使えば鍛えられる と考えるほうが建設的です。
まずは「頭がいいとは何か」を考えること自体が、すでに頭を使う練習になるかと考えて今日の記事を書いてみました。本稿が、みなさんの「頭の良さ」におけるプラスになれば幸いです。
この記事は我ながらお世辞にも頭がよさそうな文章には見えないですが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。
発表当時に出た意見など
発表中やそのあとに出た意見のメモを残しておきます。
- 計算だけで思考力が上がるかというとそれだけでは足りない。計算がうまくなるだけで終わる恐れもある。
- 計算は主に左脳の動きであり、発想やひらめきは右脳の動きである。使う部分が違う。(両方使うのが一番良いか)
- 問題を解くだけではなく、問題を作ることでより頭を使うのでは。
- 満足しているときは発想が出にくい。前提として現状に何らかの不満がないとなかなか新しい発想はでてこないかもしれない。
- 頭の使い方がいいか、頭自体がいいか、この発表は前者についての話と思われる。いわゆるIQが高いのは後者であろう。
- ジョン・ノイマンという人の話が面白いので興味ある人はググってみよう
- 一見新しい発想でも、実はそれは既存のアイデアの組み合わせであることも多い。
- リラックスも大事だが、発想力に大事なのは何より様々な経験をこなして引き出しを増やしていくこと。インプットに時間を使っていくことが必要。
- 脳内キャッシュを増やしていく。明石家さんまさんが良い手本。常にこう来たらこう返すといういろんな返しを日頃から考えて備えている。
- 半歩先が一番うける。一歩だと誰もついてこれない。意図的にこれを行うためにはまずは一般的と思われるラインがどこまでかを知る必要がある。いきなり奇抜なことをやろうとしてもダメ。
- 変わってるということは武器にもできる。既成概念に縛られない。
- 集中力も必要な要素。頭がいい人は集中もできている。
- 努力できることも能力である。
公開後の感想
ということで昔書いた記事の再掲でした。
正直、思ったよりちゃんとしてたという感想です(^^;)
再掲にあたり多少は推敲しましたが、ほぼ当時のトーンのままではあります。
お読みいただいた方、ありがとうございました。
 Jpsern.com
Jpsern.com